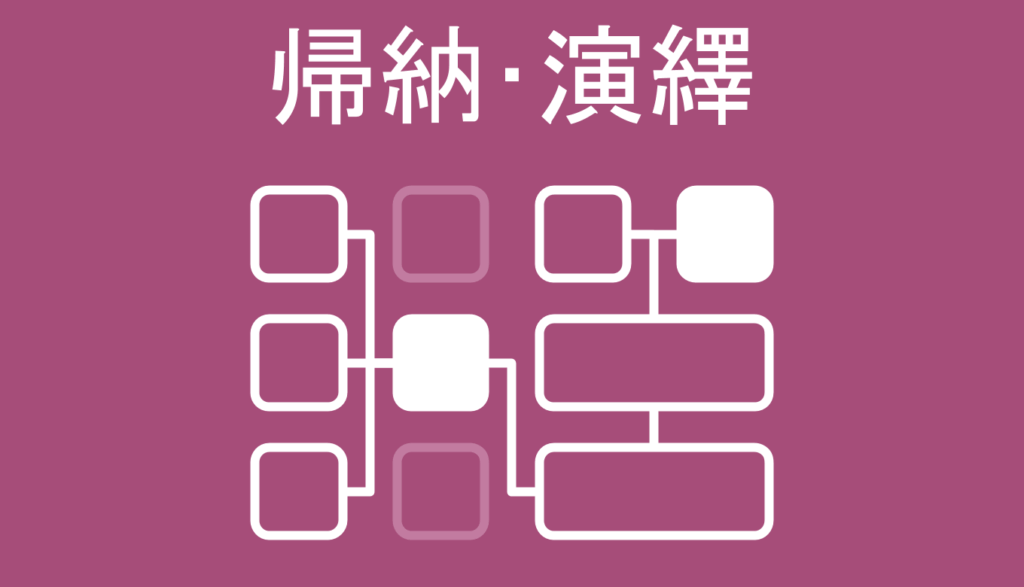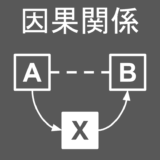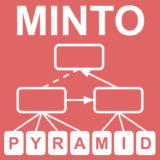だいぞう
だいぞう
演繹法と帰納法の違いを一言で表すと、
- すでに知っていることから想像するのが演繹法(えんえきほう)
- 起こった出来事からパターンを見つけるのが帰納法(きのうほう)
です。
演繹法と帰納法の違い
演繹法(えんえきほう)そして帰納法(きのうほう)は、ロジカル・シンキング(論理的思考)でよく登場する言葉です。でも、どちらがどちらなのかわかりにくい用語ですよね。
それぞれ、
- 演繹法:一般論を使って出来事の結果を推測する
- 帰納法:複数の出来事とその結果から規則性を見つける
という違いがあります。
でも両方覚えようとすると面倒なので、
- パターンを見つける帰納法
だけ覚えておいてください。
それでは図を見ながら、違いを確認していきましょう。
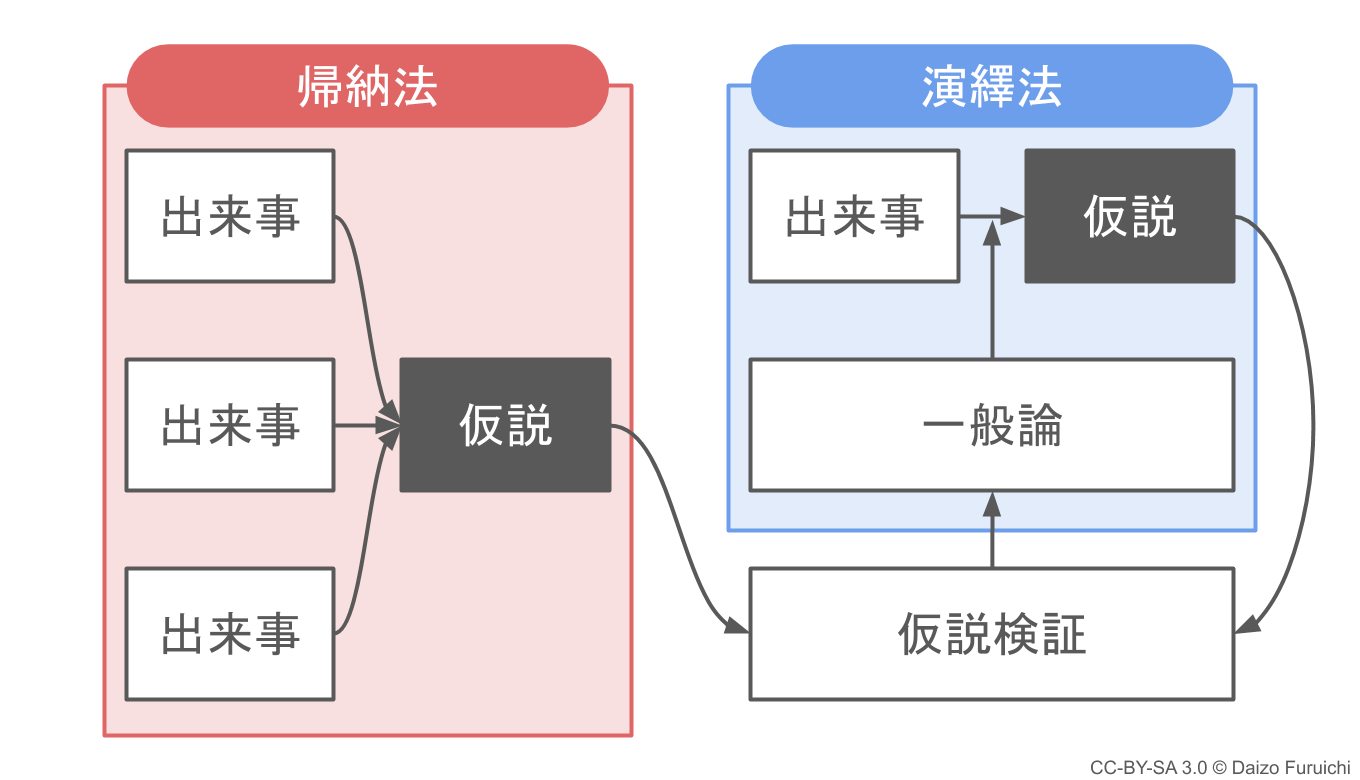
まず帰納法(きのうほう)を見てみると、起こった出来事だけで仮説を立てることができるのがわかります。
例えば、
- 出来事:一昨日はミカンが5つ売れた
- 出来事:昨日はミカンが5つ売れた
- 出来事:今日もミカンが5つ売れた
- 仮説:だからこの時期は毎日ミカンが5つ売れるだろう
というのが帰納法の考え方です。
すでにわかっていることが判断のベースになるので、パターンさえ見つかれば推測することができます。逆にまだ起こっていないことは、帰納法で推測することができません。
一方で演繹法(えんえきほう)は「一般論」を必要とします。すでにわかっていることから理論を展開するので、仮説の精度は帰納法より高くなります。
例えば過去数年のデータから、
- この時期には毎日ミカンが5つ売れる
ということがわかっていれば、それを推測の根拠に使います。
そのため論理の展開は、
- 一般論:この時期には毎日ミカンが5つ売れる
- 出来事:今日もミカンが売れている
- 仮説:だから今日は5つのミカンが売れるだろう
となります。
ここで注意しなければならないのは、推論はあくまで「仮説」だということです。「仮説」は「仮説検証」することで「一般論」になります。
このように、演繹法と帰納法の大きな違いは、すでにわかっていることである「一般論」を推測に使うかどうかになります。
4タイプの推論
ここまでご紹介した演繹法と帰納法の他にも、物事を推測するための手法が存在しています。
演繹法と帰納法を含めた代表的なものが、
- 演繹法:一般論を使って出来事の結果を推測する
- 帰納法:複数の出来事とその結果から規則性を見つける
- アナロジー:別の似ている事例から結果を推測する
- アブダクション:結果と一般論から起こった出来事を推測する
の4つです。