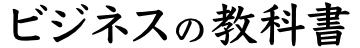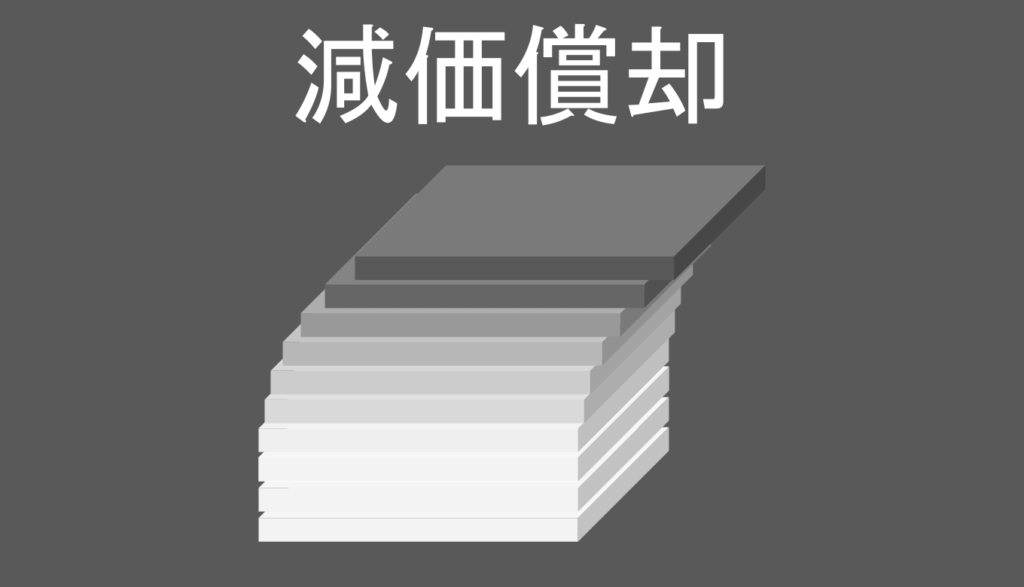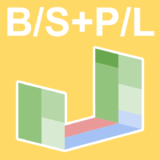だいぞう
だいぞう
減価償却とは、
- 固定資産の価値の減少を費用として計算する会計処理
のことです。
減価償却とは?
減価償却(げんかしょうきゃく)とは、機械設備や建物、ソフトウェアといった固定資産を会計ルールに則って、長期にわたって処理していく手法のことです。
英語では
- 有形固定資産の減価償却:Depreciation(ディプリシエーション)
- 無形固定資産の減価償却:Amortization(アモータイゼーション)
というように、有形なのか無形なのかで言葉を使い分けるようです。
機械設備や建物などの長く使う固定資産は、会計ルールによって購入した年度に一括して費用にすることはできません。
そのため購入した時の費用は、長期にわたって「減価償却費(げんかしょうきゃくひ)」という費用として計上します。
実は減価償却は、任意の会計処理であり、しても、しなくても問題ありません。(※個人事業主は必ず減価償却をする必要があります。)
減価償却費を計上しない場合は、その分費用が減るので利益率が向上します。一見すると良いことのように思えますが、デメリットも存在しています。減価償却のメリット・デメリットについては後述します。
減価償却の計算の流れ:自動車を購入した年度の会計処理
ここからは減価償却の具体例として、
- 年度の始めに300万円の自動車を現金で購入
- その自動車の耐用年数は3年
- 3年経っても自動車を使い続ける
という場合で計算の流れを説明します。(耐用年数は自動車のタイプごとに違います。ここでは説明や計算をわかりやすくするために300万円で3年という設定にしています。)
では、まず最初に「自動車(車両運搬具)」の購入です。
この購入は「x1年度」の一番最初の日に行われたとします。自動車の購入費 300万円は現金で支払われ、自動車そのものは会社の固定資産になります。
そのため貸借対照表の、
- 流動資産の「現金預金」が 300万円減少
- 固定資産の「有形固定資産」(の「車両運搬具」)が 300万円分増加
します。
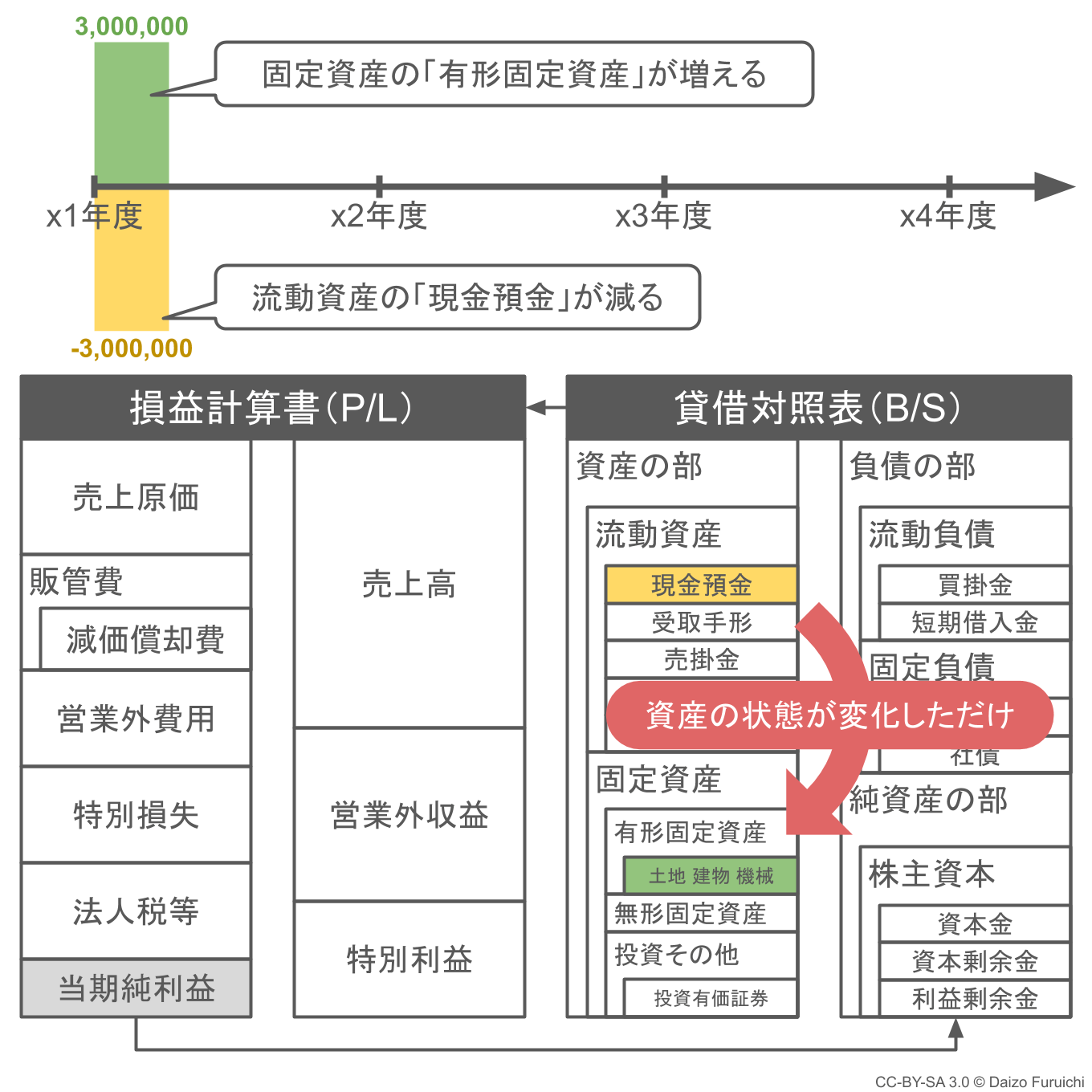
この段階でお金は外に出て行っているものの、貸借対照表の上では、
- 「現金預金」が「車両運搬具」に置き換わっただけ
と考えます。
つまり資産が減ったわけではなく、資産の状態が変化しただけということです。
言い換えると「現金預金」と「車両運搬具」を交換してもらった、というイメージになります。
それから1年間、自動車を使い続けると価値が減ります。見た目はほとんど変わらなくても、走行距離が増えたり部品が消耗したりしますよね。
この自動車の「耐用年数」は3年と決められているので、1年経つと価値が3分の1減ってしまいます。
そのため「x1年度」の最後の日(期末)には、資産の価値が300万円から200万円に「100万円」減ってしまいました。
そしてその減った「100万円」は、貸借対照表の「車両運搬具」の「減価償却累計額」として記録されます。そのため会社の資産そのものが「100万円」減ることになります。
さらに、その「100万円」はその年の商売に必要だった費用として、貸借対照表の「減価償却費」として計上されます。
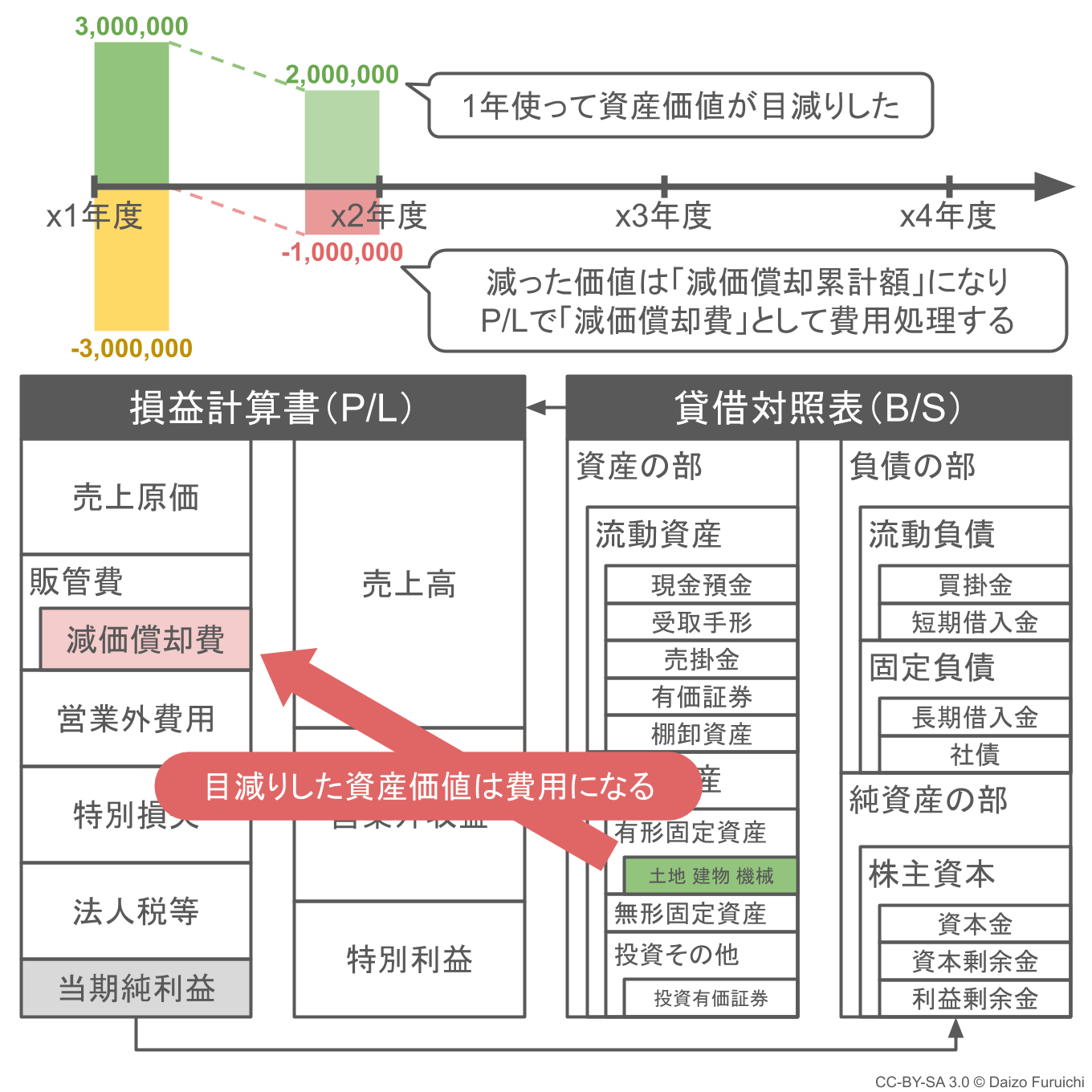
ちなみに今回の例では、
- 「販管費(販売費及び一般管理費)」の「減価償却費」
として処理されていますが、製造などに直接関わる装置や工場は、
- 「売上原価」の製造原価として計算された「減価償却費」
として処理する必要があります。
ここまでの流れをおさらいすると、その年度の初めに購入した自動車は、
- 固定資産の「有形固定資産(の車両運搬具)」として計上される
- 1年間で減った価値に相当する「車両運搬具」が減って「減価償却累計額」が増える
- その減った価値がその年の商売に必要な費用だったとみなされる
という流れで減価償却費の処理がされます。
では、翌年度以降の処理はどうなるのでしょうか?