 だいぞう
だいぞう
逆に「手段が目標になる」なんて言葉は聞いたことがありません。それには理由があります。
ざっくりと「目的」と「目標」の違いをまとめものが、こちらの表です。
| 目的 | 目標 |
| 最終的な状態 | 途中経過 |
| 終着点 | 経由地 |
| 方針の根拠になる | 手段に影響される |
| 戦略に関係 | 戦術に関係 |
| 数値化しにくい | 数値化しやすい |
| 1つの戦略に複数存在 | 1つの目的に複数存在 |
ここからは定義も含めて、詳しく関係性を見ていきましょう。
目的・目標の違いをイメージしてみよう!
まずは言葉の意味を知って、目的と目標の違いをイメージしてみましょう。
目的
目的とは、
- 実現させたい最終的な状態
のことです。
まずは登山に例えて考えてみましょう。
一般的に「登山の目的」を考えると、
- 登頂(山頂に到達すること)
をイメージする方が多いかもしれません。

しかし実際には、人が山に登る理由は様々です。
- 日頃のストレスを解消すること
- 眺めのいい景色を楽しむこと
- 健康のために足腰を鍛えること
- 親しい仲間たちと時間を過ごすこと
- 登山家としての実績を積むこと
などなど、色々な理由があります。これは、それぞれの人によって「登山の目的」が違うからです。
そしてこの「理由」こそが「実現させたい最終的な状態」である「目的」を表しています。
つまり、
- 日頃のストレスが解消された状態
- 眺めのいい景色を楽しんだ状態
- 足腰を鍛えてより健康的な状態
- 親しい仲間たちと時間を過ごせた状態
- 登山家として実績が積まれた状態
が「実現させたい最終的な状態」であり「登山の目的」になるということです。
もちろん、山に登る理由が登頂するためであれば、登頂が登山の目的になります。これをもう少し厳密表現すれば、「山頂に到達した状態になることが目的」と言えます。
具体的にビジネスで考えてみると、
- 自社ブランドの認知度を向上させる
という戦略目的を掲げた場合は、
- 自社ブランドの認知度が現在よりも高くなった状態
が実現させたい状態であり、目的になります。
しかし「目的」は、とても「抽象的」でもあります。目的だけでは曖昧な部分が多く、具体的ではありません。
その「抽象的」なイメージを「実現」につなげるために必要なのが、次に説明する「目標」です。
目標
目標とは、
- 目的に到るまでの様々な中継地点
のことです。
ここでは「山頂に到達した状態になること」を「目的」として「目標」を考えてみましょう。
山頂という終着点を目指す場合、ルートの途中で経由する「経由地A」「経由地B」「経由地C」が目標です。例えば、登山道の途中にある「〇合目」「標高〇〇メートル」のような標識をイメージするとわかりやすいと思います。
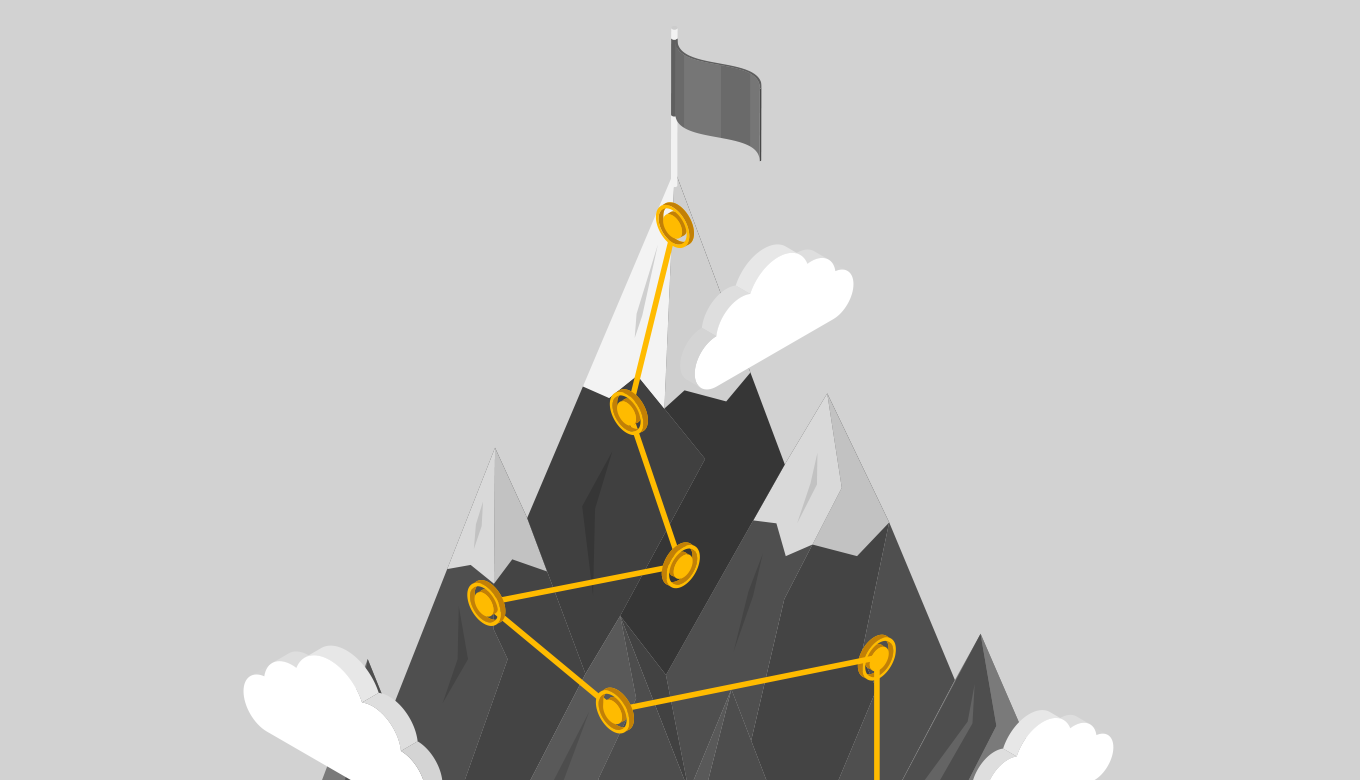
もし「経由地B」への道のりが崖崩れなどで通れない場合は、新たに「経由地D」という目標を定めることもできますし、別のルートで直接「経由地C」に向かうこともできるかもしれません。
また複数のチームで一つの目的を目指している場合は、それぞれ違うルートで違う目標を達成しながら進むこともあります。
ビジネスで例を挙げると「自社ブランドの認知度を向上させる」という「目的」に対して、
- 自社製品Aの認知度をターゲット層の70%まで高める
ことが「目標」である場合は、
- 自社製品Aの認知度 = 70%
という状態を目指しているわけです。
つまり「目標の達成」は、
- 認知度 70%という地点を経由する
ことが目的までの進捗状況を知る目安であり、70%を通過すれば今度は80%とまた別の目標が現れます。
「ゴール(Goal)」は「目的」と「目標」の両方に使える言葉
「Goal」という英語を日本語に訳す場合、
- 目的
- 目標
の両方の意味で訳すことができます。
しかし「目的」も「目標」も日本語では違う意味なのに、なぜ1つの言葉で表せるのでしょうか?
それは、ゴールが本来持っている意味が、
- 到達すべき「領域」や「範囲」
のことを指すからです。
これはマラソンやサッカーのゴールなどをイメージすると、わかりやすいかもしれません。
マラソンのゴールはゴール地点に引かれてあるラインを越えて、その先の領域に到達すればゴールになります。サッカーのゴールは、ゴールポストとクロスバー、ゴールラインで囲まれた領域の向こう側にボールが到達すればゴールです。
いずれも、領域に入ればゴール達成になります。これは「Goal」の語源が、中世英語の「gol(境界、限界、領域)」に由来するためです。
目的としてのゴールは、「実現させたい最終的な状態」そのものが、到達するべき「領域」や「範囲」になります。
例えば、「長めのいい景色を楽しむことが登山の目的」であれば、「景色を楽しめた状態」と「景色を楽しめなかった状態」の間に「境界」が存在しています。その境界を超えて「景色を楽しめた状態」になっていれば、「目的を達成した」ということになります。
目標としてのゴールは、「目的に到達するまでの途中の経由地」であり、通過するべき「領域」や「範囲」になります。
例えば、「長めのいい景色を楽しむことが登山の目的」に対して、5合目の展望台を目指すとすれば、「1合目」「2合目」「3合目」「4合目」が「目標」になります。
ちなみに「合目(ごうめ)」とは、モノとモノを合わせたつなぎ目を表す言葉であり、山では登山の道のりをエリアで区切って、そのエリアとエリアの境界にある地点を「合目」と呼んでいます。
つまり「合目」も「境界」を表している言葉であり、その境界を超えて新たな「領域」や「範囲」に突入することが「目標の達成」になります。


