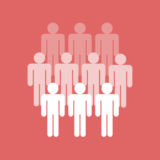だいぞう
だいぞう
集積の経済とは、
- 同じ地域に様々な企業が集まることで得られる経済効果
のことです。
逆の効果を「集積の不経済」と呼びます。
集積の経済によるメリット
集積の経済(Economies of agglomeration)とは、
- 特定の地域に様々な企業が集まることで経済的なメリットが生じること
です。
「集積の経済性」とも呼ばれ、集積した企業の間での取引が効率的になり、色々なコストが軽減されます。
また集積の経済が生まれている地域には、さらに企業が集まって経済性が強化されます。
わかりやすい例としては、
- 駅前には様々な会社の事務所が立地している
- 町工場がたくさん密集している地域がある
- コンビナートに様々な工場が密集する(サプライチェーンの集積)
などなど、身の回りにたくさんあります。
集積化が起こるとその地域に、
- 資本
- 企業
- 顧客
- 労働力
などがどんどん集まります。集まることで、どの企業も効率的にそれらの資源にアクセスすることができるようになります。
集積の経済性の効果としては、
- 輸送費が下がる
- 顧客や取引先が増えて営業効率が上がる
- 労働力が確保しやすくなって採用コストが下がる
- 知識やノウハウが人を通じて流動して発展する
などが考えられます。
集積の不経済とデメリット
たくさんの企業が同じ地域に集まることで、デメリットも生じます。
- 環境負担が集中する(工場の集積)
- 道路の渋滞など公共インフラの負担が増える
- 地価が上昇して賃料に圧迫される
- 同業者同士の競争圧力が高くなる
などが考えられます。
環境負担や公共インフラの負担については、集積した企業が収める税金で対応することになります。
また賃料の上昇は、集積による効率化による効果が上回れば問題になりません。
同業者同士の競争圧力については、価格競争に陥るという側面もありますが、技術力や品質の向上などを見込むことができます。
ポーターのクラスター理論
集積の経済を発展させた考え方として、マイケル・ポーター教授の「クラスター理論」というものがあります。
クラスター理論では地理的な企業の集積によって、効率化だけでなく競争力を手に入れることができると考えます。
例えばシリコンバレーに立地する先端企業と、途上国に立地する先端企業を比較すると、
- 採用できる人材の技術力に大きな差がある
- ベンチャーキャピタルから受けられる支援に差がある
- 他の企業や教育機関と連携できる機会に差がある
- 取引できる顧客の規模に差がある
などなど、立地を変えるだけで競争優位性が全く変わってきます。そのため、企業がどのようなクラスターに属しているかで、経営戦略も大きく変わります。