 だいぞう
だいぞう
「製品」と「商品」の違いは、
- 売り物として扱われているかいないかの違い
で、「サービス」は
- 物質として形がない「製品」または「商品」
です。
ここからは、製品・商品・サービスの違いを図解しながら説明します。
製品・商品・サービスの違いを図解
まず「製品」と「商品」は、
- 製品:原材料などを加工して製造されたもの
- 商品:売買の対象として扱われるもの
という違いがあります。
「製品」は、直接売られるかどうかに関わらず、製造されたものを指します。
一方で「商品」は、売買の対象になれば何でも「商品」と呼べます。
例えば、その辺に落ちている石ころを拾って誰かと取引しようとすれば、その石ころはその瞬間から「商品」になります。また、あなたが時給をもらって何かの手伝いをするのであれば、あなたの「時間」と「労働力」が「商品」になります。
逆に売る気がなければ「製品」だったとしても「商品」にはなりません。
例えば、世界で5台しか製造されなかったレアな自動車があるとします。もしその自動車を買った人が誰も売ろうとしなければ、その自動車は二度と「商品」になることはありません。
しかし誰かがその中の1台を手放そうと、オークションにかけたとします。そうすると、そのオークションに出した1台だけは「商品」となります。
これを図で表すと、以下のようになります。
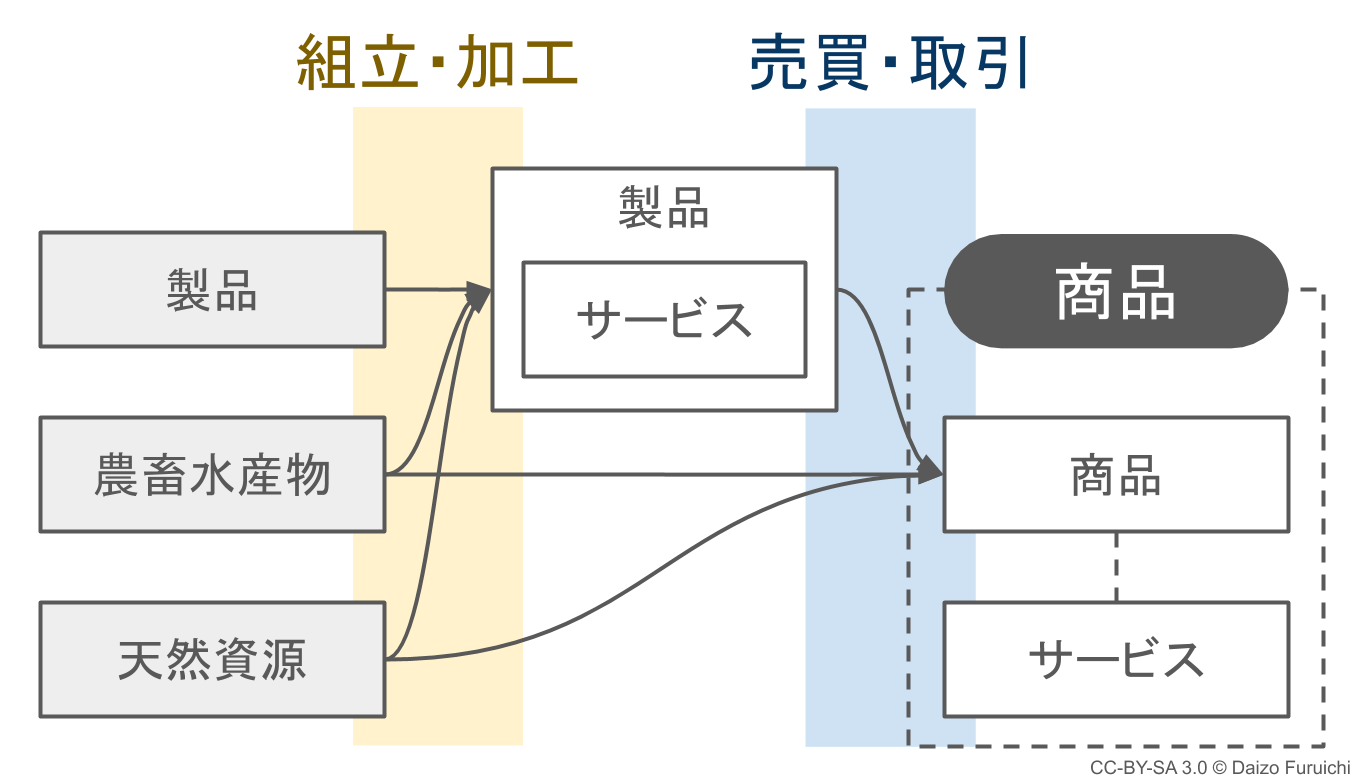
さらに「製品」も「商品」も、
- 広い意味(広義):サービスも含める
- 狭い意味(狭義):サービスは含めない
という特徴があります。
表にしてみると以下のような感じです。
| 製品 | 商品 | |
| 広義 | 製品 + 付随サービス | 商品 や サービス |
| 狭義 | 製品のみ | 商品・品物・物品 |
広い意味での「製品」とは、
- 製品 = 製品そのもの + 製品に付随するサービス
ですが、狭い意味の「製品」は、
- 製品 = 製品そのもの
になります。ただし、サービス部分だけを指して「製品」と呼ぶことはほぼありません。
広い意味での「商品」とは、
- 商品 = 形のあるもの + 形のないもの
ですが、狭い意味の「商品」は、
- 商品 = 形のあるもの(商品・品物・物品)
- 商品 = 形のないもの(サービス)
というように、どちらか一方だけでも「商品」と呼ばれます。
製品
製品とは、製造工程を経たモノのことです。通常は部品などを組み立てたり、原料を仕入れて加工などをした後の状態を指します。原料の他にも、他の会社が作った製品を加工することで、別の製品を作り上げたりもします。
英語では、
- 生み出す = Produce(プロデュース)
が転じて、
- 製品 = Product(プロダクト)
となっています。
つまり生み出されたものを指して「製品(Product)」と呼んでいます。
例えば「電気製品」や「加工製品」などが、わかりやすい例です。
電気製品には金属・プラスチック・樹脂などが使われていますが、原料の鉱石や石油から部品を作るメーカーはほとんど存在しません。どこかの会社が金属やプラスチックを作り、また別の会社がそれらを部品に加工します。それを大きなメーカーが仕入れて最終加工や組立を行います。
このようにサプライチェーン(供給連鎖)の中を流れるものを「製品」と呼びます。
しかし、形のあるものだけが製品ではありません。製品には品質を保証したり、輸送を代行したりなどの「サービス」が付随することもよくあります。
広い意味では、サービスを含めて「製品」と呼びます。また、狭い意味で形のあるものだけを指して「製品」と呼ぶこともあります。ただし、サービスだけを指して「製品」と呼ぶ場面はほとんどありません。
商品
商品とは、顧客の目の前に提示したモノやサービスのことです。
英語では、
- 商人 = Merchant(マーチャント)
が売買で取り扱っているものすべてを、
- 商品 = Merchandise(マーチャンダイズ)
と呼んでいます。
そのため「製品」以外も商品になります。農作物や天然資源は、取引の対象となった瞬間から「商品」になるため、「製品」にならないまま「商品」となります。
例えば、畑で採れた野菜は、作った人が自分で食べてしまうのであれば「商品」ではありません。しかし値段をつけて棚に並べた瞬間に「商品」になります。石炭や石油も同様で、地中に埋まっているだけではただの天然資源ですが、掘り出す権利や資源そのものに値段がついた瞬間に「商品」となります。
また形のあるものだけを指して「商品(Merchandise)」と呼ぶこともあれば、サービスだけでも「商品(Merchandise)」と呼ぶこともあります。
一般的に形のある商品は、
- 商品
- 品物(しなもの)
- 物品(ぶっぴん)
などと呼ばれます。
そして形のない商品は、
- 商品
- サービス
などと呼ばれます。
形があっても無くても「商品」と呼ばれることがあるので、文脈や状況から判断する必要があります。
サービス
サービスとは、役務(えきむ:他者のために行う労働)のことです。
サービスには4つの特性があると言われています。
- 無形性(非有形性):形がなく目に見えないし触れない
- 消滅性(非貯蔵性):形がないので貯めておけない
- 変動性(非均一性):需要と供給の量や質にバラツキがある
- 不可分性:サービスの提供と消費は同時であり切り離せない
書籍によって呼び方が少し違ったり「変動性」が需要と供給で2つに別れていたりしますが、ほぼ同じ内容が説明されていると思います。
ここでもう一度「サービス」という言葉の位置付けを考えてみると、
- サービスだけでビジネスが成り立つ = 商品としてのサービス
ということになります。
次のページでは広義の「商品」である、
- 商品 = 形のある商品 + 形のない商品(サービス)
- 商品 = 形のない商品(サービス)
の具体例と、「製品」「商品」「サービス」の言葉の使い分け方を見ていきましょう。



