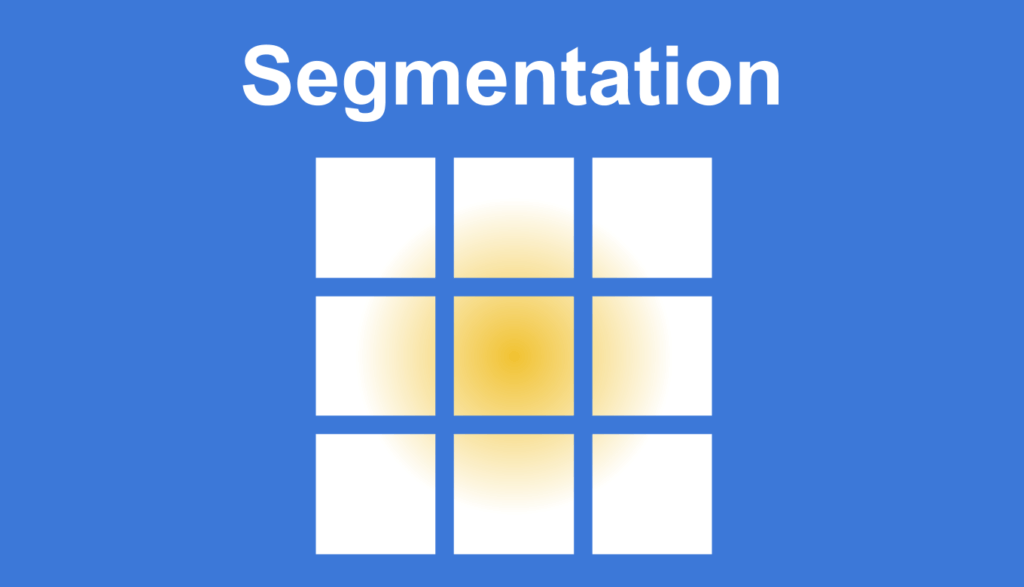だいぞう
だいぞう
セグメンテーション(市場細分化)とは、
- 市場全体の中から似通ったニーズやウォンツを持つ消費者を切り分ける
というマーケティング手法です。
市場セグメントを細かくすればするほど、
- メリット:マーケティング活動の効果を高めやすくなる
- デメリット:マーケティング活動のコストが増加する
という影響があります。
セグメンテーションでは、様々な切り口(変数)を使って市場を「市場セグメント」という小さな単位に分割します。
セグメンテーションに使われる変数は、
- ジオグラフィック変数(Geographic、地理的変数)
- デモグラフィック変数(Demographic、人口統計変数)
- ソシオグラフィック変数(Sociographic、社会的変数)
- サイコグラフィック変数(Psychographic、心理的変数)
- ビヘイビアル変数(Behavioral、行動変数)
などに大きく分けることができます。
また、市場セグメントをターゲットとするための評価基準として、「Rank(ランク)」「Realistic Scale(リアリスティック・スケール)」「Reach(リーチ)」「Response(レスポンス)」の4つの条件(4R)や、コトラーの5つの評価基準である、
- 測定可能性:市場の規模を測れること
- 接近可能性:市場にアプローチできること
- 差別化可能性:市場から独自の反応が返ってくること
- 利益確保可能性:市場から十分な利益を見込めること
- 実行可能性:現実的なマーケティング施策を設計できること
などが存在します。(すぐに変数一覧と評価基準を確認したい場合→5ページ目へ移動)
ここではセグメンテーションを行うやり方について具体例でわかりやすく解説します。
セグメンテーションとは?STPの最初のステップ
セグメンテーションとは、
- 市場全体の中から似通ったニーズやウォンツを持つ消費者を切り分けること
で、日本語では「市場細分化」と呼ばれます。英語では「Segmentation」と書きます。
これは「マーケティングのSTP(エス・ティー・ピー)」と呼ばれる、
- Segmentation(セグメンテーション):市場をセグメントに切り分ける
- Targeting(ターゲティング):どの市場セグメントを標的にするか決める
- Positioning(ポジショニング):競合と差別化するための位置決めをする
という3つの流れの一番最初のステップになります。
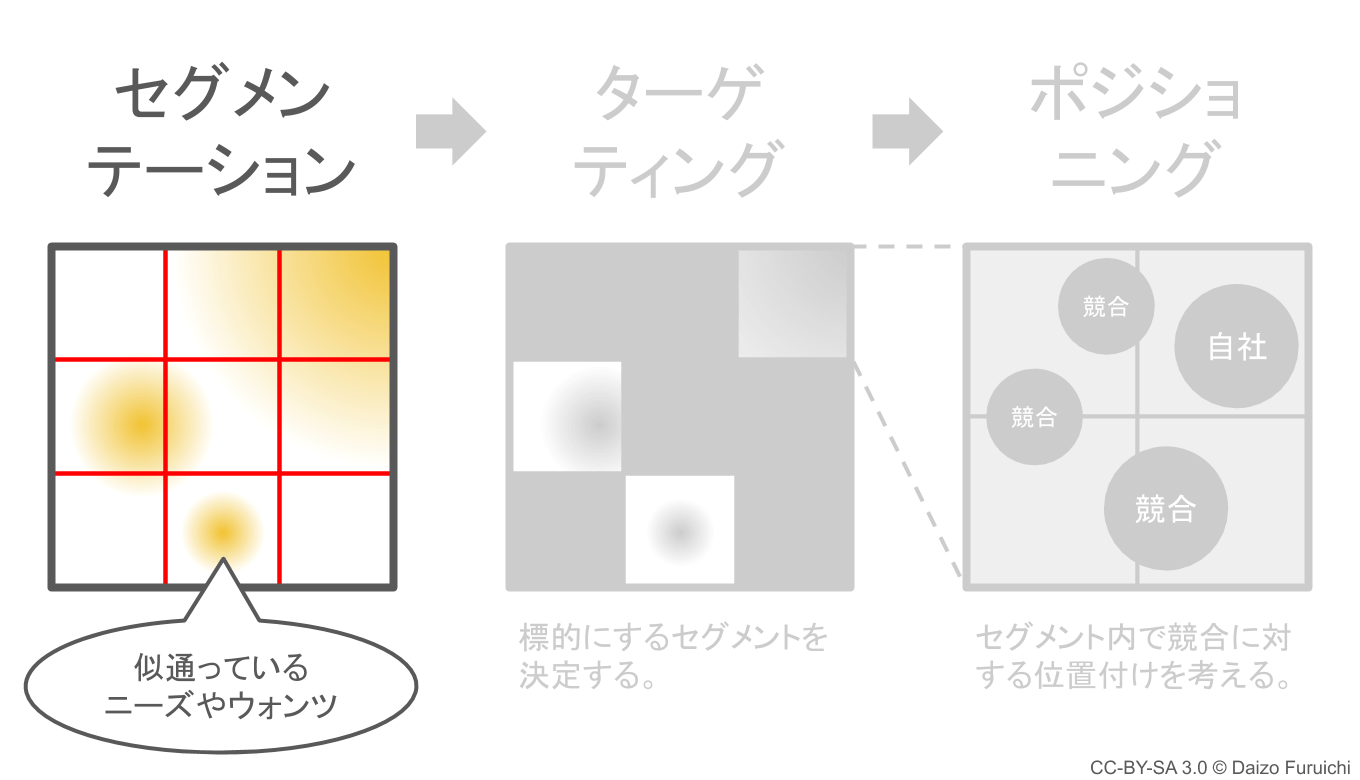
マーケティング活動を始めるために、なんでわざわざこんな面倒な「STP」のステップを踏まなければいけないかと言うと、どんな会社でもヒト・モノ・カネなどの経営資源が限られているからです。
そして経営資源に限りがあるなら、無駄遣いせずに勝ち目のある市場セグメント(細分化された市場)で戦いたいですよね。
そのためには、自分の会社にとって勝ち目のある(儲かる)市場セグメントがどこなのか、マーケティングを行う最初の段階で目星を付けなければなりません。
その目星を付けるための最初の手順が「セグメンテーション」なのです。
セグメンテーションのやり方のコツはニーズとウォンツ
セグメンテーションは、STPの流れでも一番重要なステップです。
なぜなら、最初のセグメンテーションを間違うと、そのあとの「ターゲティング(標的市場の決定)」と「ポジショニング(競合に対する位置取り)」もすべて間違ってしまうからです。
だからセグメンテーションの責任は重大。しっくりくるまでいろいろな角度から市場を切りましょう。
そしてセグメンテーションの一番重要なコツは、
- 消費者のニーズやウォンツを常に意識すること
です。
セグメンテーションの目的は、
- 市場に点在している似通ったニーズやウォンツ持った消費者グループを探すこと
なので、切り出した市場セグメントの中に共通するニーズやウォンツが含まれていれば、セグメンテーションは成功です。
でも、はじめは「成功したセグメンテーション」をイメージしづらいと思うので、図解してみました。
下の図の四角い枠が市場全体で、黄色のモヤモヤが「似通ったニーズやウォンツ」だと思ってください。
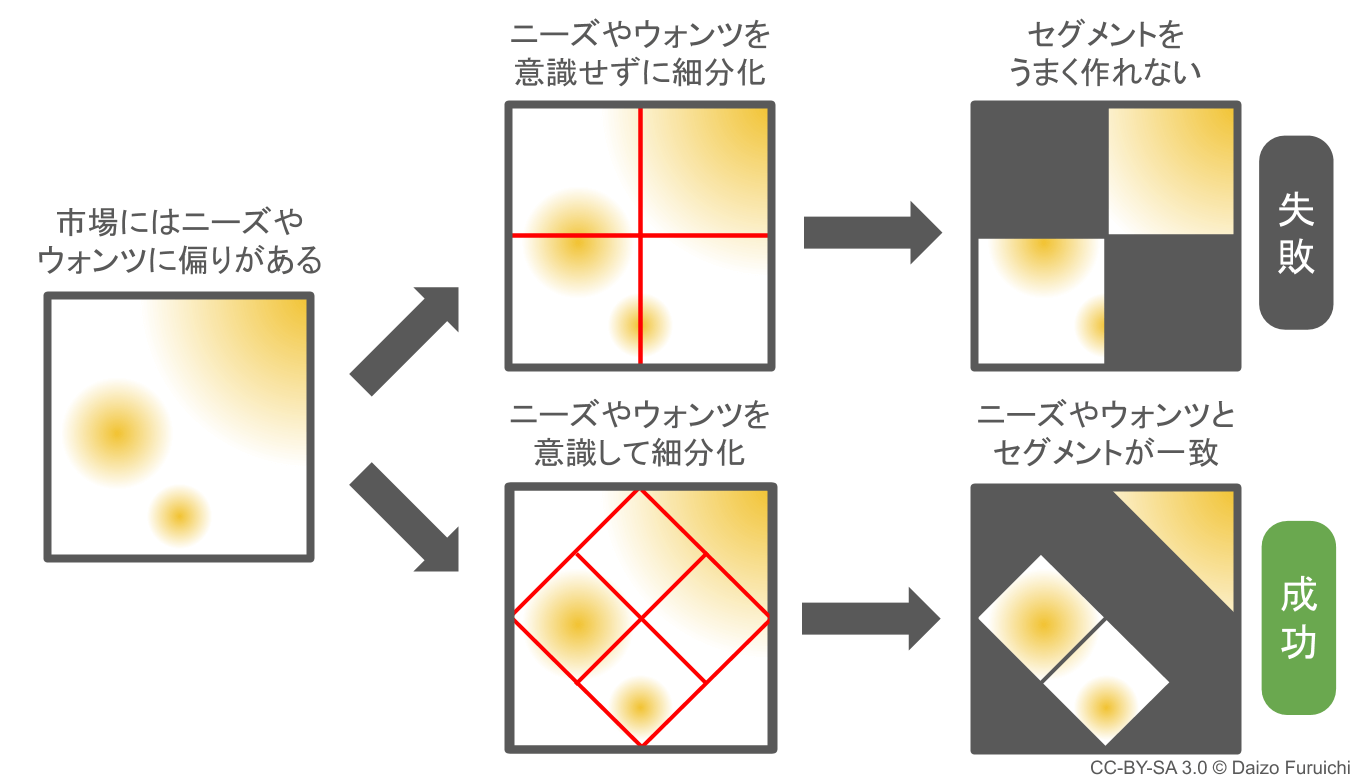
まず上段の失敗例は、
- ニーズやウォンツを意識せずに細分化した(赤い線を引いた)
ために、市場セグメントを選択する「ターゲティング」の段階で、2つの異なったニーズやウォンツを含むセグメントができてしまっています。
一方で、成功した下の段では、
- ニーズやウォンツを意識して細分化した(赤い線を引いた)
ので、ターゲティングをしても、それぞれの市場セグメントごとにニーズやウォンツがまとまっていることがわかると思います。
ちなみに上記の例では2次元で表現していますが、切り口は2つだけとは限りません。しかし逆に、多ければ良いというわけでもありません。
できるだけ少ない切り口で精、度の高い市場セグメントの切り出しができるのが理想的です。
次のページからは、架空のラーメン屋を具体例に挙げて説明しましょう。