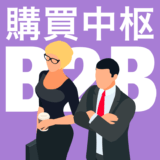だいぞう
だいぞう
B2B市場の企業顧客は、
- 価格志向顧客:価格を重視する顧客
- ソリューション志向顧客:効果や信頼性を重視する顧客
- ゴールド・スタンダード顧客:品質やパフォーマンスの基準を持つ顧客
- 戦略的価値顧客:パートナーとして長期的な関係性を望む顧客
の4つのタイプに分類できると言われています。(「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版 」p269 参照)
また似たような分類方法として、
- バイイング志向:視点が短期的で安く調達したい顧客(≒ 価格志向顧客)
- 調達志向:供給業者と協力して品質改良とコスト削減を求める顧客(≒ ソリューション志向顧客)
- サプライチェーン・マネジメント志向:サプライチェーンで戦略的に価値を高めようとする顧客(≒ 戦略的価値顧客)
の3つの購買志向に分ける考え方もあります。(ジェームス・C・アンダーソン&ジェームス・A・ナラス 著「Business Market Management: Understanding, Creating and Delivering Value 」、「コトラー&ケラーのマーケティング・マネジメント 第12版」p272 参照)
マーケターとしてB2B市場に製品やサービスを売り込むためには、組織の購買意思決定を行う「購買中枢」の購買スタイルを見極めることが重要です。
しかし同様に、購買中枢の個人だけではなく、顧客企業としての購買スタイルも見極めて提案を行う必要もあります。
とにかく価格を重視する顧客、価格だけでなく製品やサービスがもたらす効果を気にする顧客、最高の品質を求める顧客、事業の戦略的なパートナーとしての関係を望む顧客など様々です。
ここでは企業顧客の代表的な4つのタイプと、それぞれの顧客への対応について説明します。
価格志向顧客
価格志向(Price-Oriented)顧客とは、
- 価格をもっとも重視する顧客
のことです。
別の分類ではバイイング志向(Buying-Oriented)とも呼ばれ、購買担当者は製品やサービスの基準を満たし安定供給されれば、安く調達するほど社内での評価が高まります。
そのため、このタイプの顧客は、供給業者を比較し、競争させ、可能な限り価格を下げようと圧力をかける傾向にあります。
その手法(戦術)としては、
- コモディティ化:「消耗品なんだから価格次第だ」と供給業者に迫る
- マルチソーシング化:「他の業者からも調達できる」と代替業者を挙げる
などがあります。
顧客がこのような価格志向になってしまう理由としては、
- 対象の製品やサービスが価格以外で差別化しにくい
- 顧客がコスト競争力の重視される業界に属している
- 買い手である顧客の交渉力が強くなっている
といったことが挙げられます。
もし顧客が購買を検討している製品やサービスが、どの供給業者も価格以外の面でほとんど同じであれば、顧客としてはより価格の低いものを望むことになります。
また顧客自身が価格競争に巻き込まれていたり、コスト競争力が競争優位につながる業界に属している場合でも、価格志向の購買を行いやすくなります。顧客は同じものでもより安価に調達することができれば、それがそのまま顧客の利益につながります。
他にも業界構造として、顧客の供給業者に対する交渉力が高まっている場合も考えられます。例えば、供給業者にとって、その顧客が数少ない取引先の一つであれば、顧客を失うことが大きな損失につながります。そうなれば足元を見て価格交渉をする顧客も現れます。顧客は取引を続けることと引き換えに、価格を下げる圧力をかけてくるかもしれません。
売り手や買い手の交渉力については、ファイブフォース分析の記事もご覧ください。
取引販売での対応
このような価格志向の顧客に対しては、
- 購入できる量を制限する
- 払い戻しをしない・返品を受け付けない
- 価格調整をしない
- アフターサービスを提供しない
といった取引販売(Transactional selling)での対応が考えられます。
もし、とても低い金額で契約をしてしまって、その後も際限なく低価格で購買されると大きな損失につながってしまいます。そのような場合には、顧客が購入できる量を契約で制限するという方法が考えられます。初回の一定量は安く販売するといった対応も、同様の考え方になります。
また安く販売する代わりに、全て買い取ってもらう(払い戻しはしない)というのも一つの方法です。大量に買ってもらう約束で価格を下げても、返品されてしまうと目も当てられません。そういったことを避けるためにも、安く販売する代わりに返品などを受け付けないという契約にする方法があります。
同様に、低い価格を設定する代わりに価格調整を一切しないという方法もあります。
価格調整とは、
- ボリュームディスカウントや現金値引きなど条件と引き換えに価格を調整すること
です。
低価格を実現する代わりに、条件による値引きを一切受け付けないことにすれば、さらに安く買い叩かれることを避けることができます。
他にもアフターサービスなど、追加で必要となるコストを省くことで低価格を実現したり、別料金にすることで本体の低価格を実現する方法もあります。