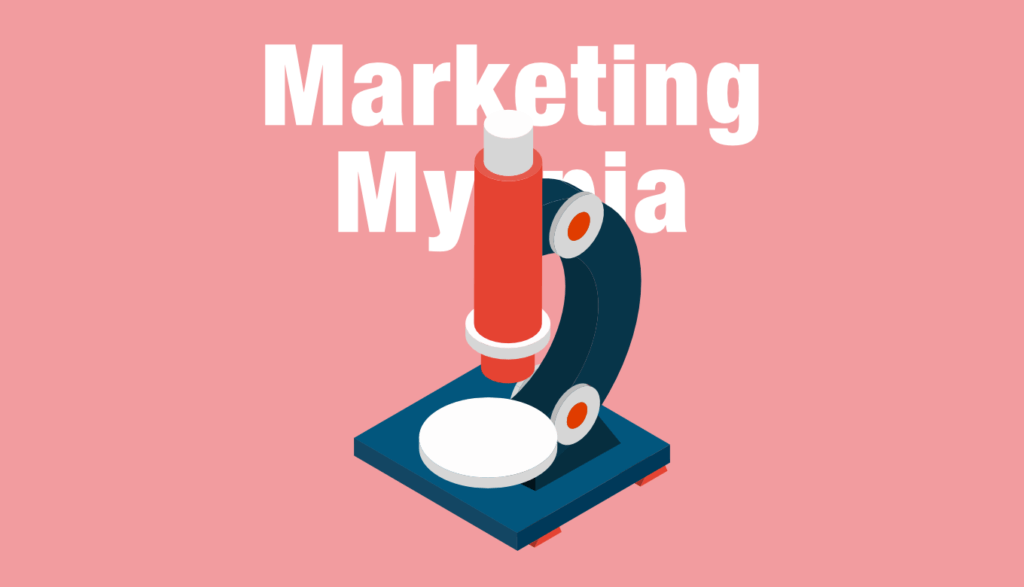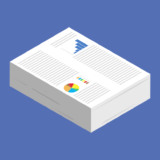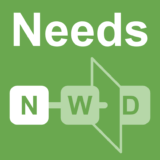だいぞう
だいぞう
マーケティングマイオピアとは、企業が製品を中心に考えようとする「製品志向」の自己欺瞞(ぎまん)に陥ってしまい、顧客が何を求めているかを考える「顧客志向」がおろそかになってしまう状態のことです。
1960年に、ハーバード大学ビジネススクール教授のセオドア・レビット氏が発表した論文「Marketing Myopia」で広まった考え方で、日本語では「マーケティング近視眼」や「近視眼的マーケティング」とも呼ばれています。
このマーケティング近視眼に陥ってしまう理由としては、
- 市場の拡大が確実なものと信じ切ってしまう
- 主要製品に対する代替品が存在しないと考えてしまう
- 大量生産によるコスト優位性に頼り切ってしまう
- 研究開発・製品改善・製造コスト削減に夢中になってしまう
の4つの原因が挙げられています。(レビット著「Marketing Myopia」より翻訳)
マーケティングマイオピアにならないためには、これらの4つの原因を避ける必要があります。
ここでは、レビット教授の論文「Marketing Myopia」を読み解きながら、マーケティング近視眼について解説します。
マーケティングマイオピアとは?
マーケティング近視眼(マーケティングマイオピア)とは、
- 既存製品を中心に考える「製品志向(product-oriented)」に極端に傾倒してしまい、「顧客志向(customer-oriented)」的な視点がおろそかになってしまう状態
のことです。
「製品志向」や「顧客志向(マーケティング志向)」のより詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
マイオピア(Myopia)とは、医学的には「近視」という意味ですが、一般的には「視野の狭さ」というという意味で使われる英単語です。つまり、マーケティングマイオピアとは、マーケティングに対する視野が狭くなっている状態を表現しています。
この「マーケティングマイオピア」という考え方は、1960年に、ハーバード大学ビジネススクールの教授であるセオドア・レビット氏が、論文誌の「ハーバード・ビジネス・レビュー(Harvard Business Review)」に寄稿した論文「Marketing Myopia」で広まりました。
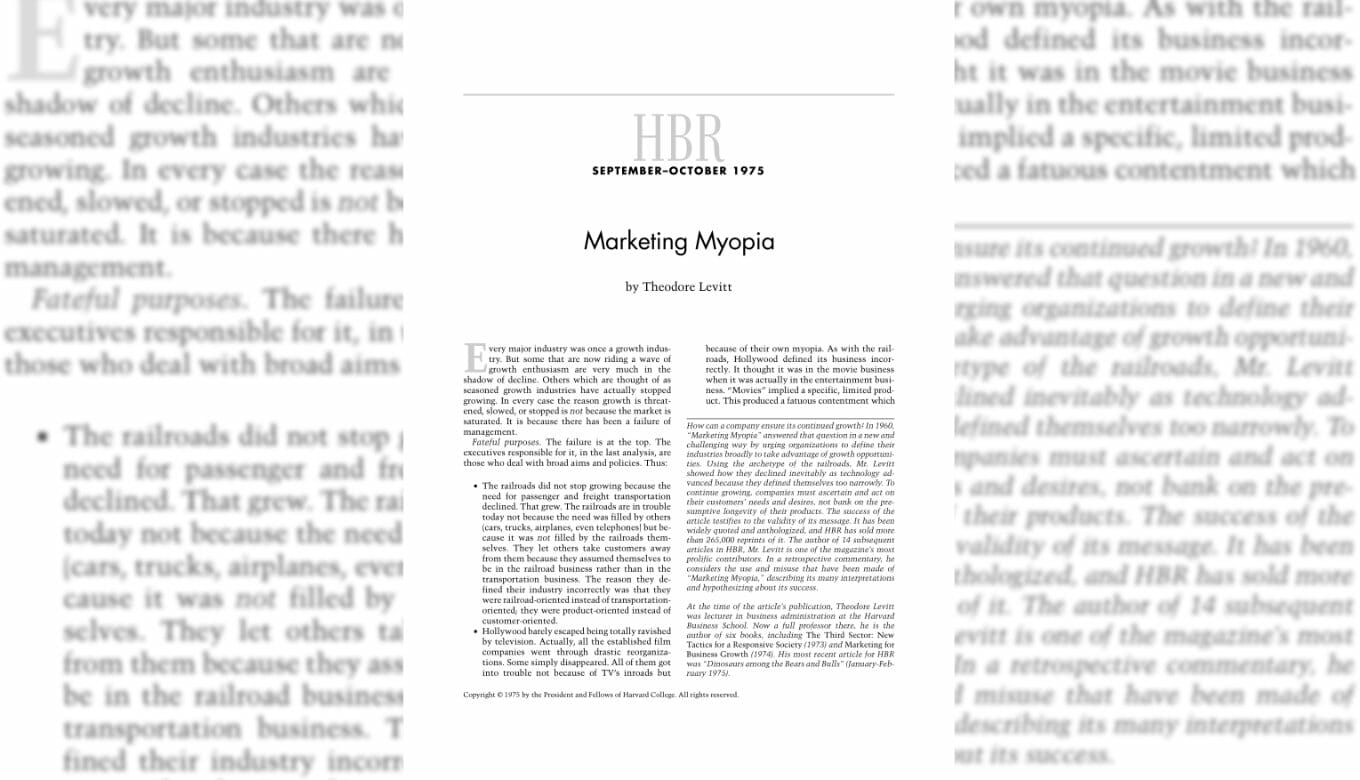
筆者の手元にあるものは、1975年に論文誌ハーバードビジネスレビューに再掲された上記の論文です。こちらは1960年のオリジナルの論文に加えて、レビット教授の回顧録も掲載されている記事になります。
またこの論文は、ハーバードビジネスレビューに何度も掲載されているようで、下記のリンクから2004年に再掲された時のものを有料でダウンロードすることができます。
参考
Marketing Myopia by Theodore LevittHarvard Business Review
ちなみに、1975年掲載分と2004年掲載分のいずれも、論文自体は1960年に発表されたものなので、どれを読んでも内容は同じです。
また日本語訳は下記の書籍に掲載されています。